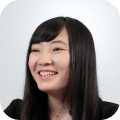キラリな仕事と先輩たち 仕事・先輩について
 社員紹介
社員紹介
入社動機 | 業界屈指の技術を誇る工場設備に圧倒

学生時代は、屋外を自律走行するロボット分野の開発に打ち込んでいました。「物体検出」を研究テーマにし、歩行者信号の認識や道中に落ちているゴミの種類の判定の研究を行っていました。
プログラムと向き合う毎日を送る中で、よく食べていたのがカップめんでした。就職活動の当初は、機械メーカーを志望していましたが、自分にとって身近にあるものを仕事にしたいと思うようになり、カップめんや即席めんを扱う食品メーカーに気持ちが向いていきました。また、そういった商品はコンビニやスーパーなどで目にする機会も多いので、やりがいに感じるという思いもありました。
明星食品の選考過程では、工場見学がありました。いろいろな発見がありましたが、中でも興味が湧いたのは、製造ラインの速さです。製造ライン上には製品がカーブする箇所もありますが、スピードを落とさずに滞りなく製品が流れていました。業界屈指のスピードを誇る設備だという説明を聞き、その技術力の高さに圧倒されました。生産技術部の先輩が親切に案内してくださったことも相まって、ここで働きたいという気持ちが強まりました。
仕事のやりがい | 担当した設備が無事に導入できて得られる達成感
入社2年目から、AIを活用した自社開発設備の開発チームに所属しています。まさか食品業界で、学生時代に頑張ったプログラミングの経験を生かせる日が来るとは思いもしませんでした。
開発チームは発足から日が浅く、メンバーが持っている技術はバラバラでしたし、みんな独学で勉強した人たちばかりです。どういう技術を用いるのか、といったところから議論を始めるなど、試行錯誤しながら開発を進めていかざるを得ませんが、逆に、一つひとつ模索しながらつくり上げていくところに、仕事のやりがいを感じています。
設備の導入や更新においては、慎重さが何よりも大事です。もし、設備に何か一つでも不具合が生じ、製造ラインがストップしたら、生産に影響してしまいます。そのため、設備を工場に導入する際には、仕様を決める段階からあらゆる状況を想定します。機器メーカーとの打ち合わせは綿密に行い、設備の動作確認においても、条件を変えて一つひとつの動きを確認します。製造当日に、設備が安定して動く様子を見届けるまで気を抜くことはできません。その分、商品ができ上がっていく様子を見ると、大きな達成感を得ることができます。

今後のビジョン | 自社開発設備の実績を積み、他工場へ展開する

自社開発の設備は埼玉工場で運用されていますが、今後はグループ企業を含めて、他の工場にも展開することを目標にしています。さらに、開発の分野を広げることにも挑戦してみたいですね。
そうした実績を積み上げることで、グループ全体の生産性の向上に貢献するだけでなく、ITやプログラミングを学ぶ学生たちに、「食品業界でもITの技術を生かすことができるんだ」という認識を少しでも広げたいと考えています。今はまだプログラミングを学ぶ学生たちの将来の選択肢に「食品業界」は入っていないかも知れませんが、自分たちが先駆者となって成果を上げることで、「この業界で活躍したい」と考える学生が増えれば、開発力の底上げにもつながってくると思います。
私の仕事
- 開発研究所生産技術部の担当業務
埼玉工場の担当です。工場への設備の新規導入や更新の計画を立て、設計と施工を行います。また、工場の設備は固定資産のため、資産管理の一環として経理業務なども担います。
入社2年目からは、設備の自社開発に携わっています。カップめんの製造過程で製品に汚れが付着していないかを、AIを用いて検出する外観検査を行っております。導入の要件定義から部品発注まで、幅広く業務に取り組んでいます。プログラミングを行うため、業務を通じて専門的な知識の習得にも励んでいます。
- こんな仕事をしています
- 自社開発装置の動作確認
出社してから最初にするのが、装置の動作確認です。
ログなどを通して、装置が正常に動いているかをチェックします。 - 機能検証とエラー対応
アプリケーションに機能追加をする際は、まずはテスト機で試します。それで問題なく動くことを検証できてから、工場にある装置を更新します。テスト機での検証でエラーが起きた場合は、何が原因だったかを調べて対応します。 - 機器メーカーとの打ち合わせ
機器メーカーとは、設備の仕様決めや工事などの打ち合わせを行います。専門用語が飛び交うため、入社したばかりの頃は内容を理解できず、かなり苦労しました。そのため、実際に工場へ足を運び、設備の仕組みを改めて確認したり、上司や工場のオペレーターの方に質問したりして、専門知識を身に付けていきました。
- 自社開発装置の動作確認
- モットーは「徹底したリスク管理の実践」
製造に影響する業務を行っているため、トラブル回避は最重要項目です。そのためにも、徹底したリスク管理をモットーにしています。設備を導入する際にも、メーカーの意見を100%うのみにするのではなく、他の設備との兼ね合いも含めて、装置が止まってしまうことがないよう、あらゆるリスクを考慮して計画を立てるとともに、不安要素がなくなるまで確認を行います。こうした地道な作業があってこそ、「この設備は問題なく動く」と自信を持って、工場に送り出すことができます。